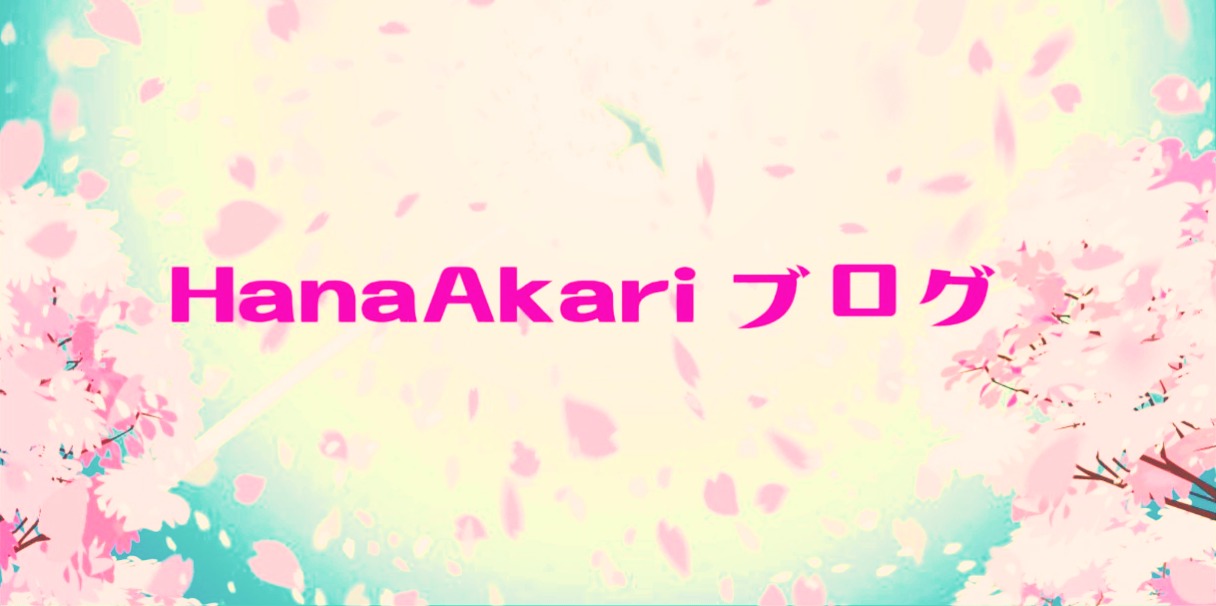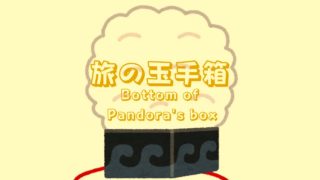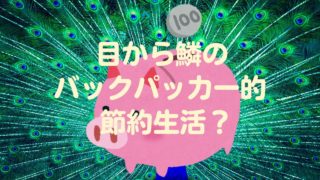このブログは私がバックパッカーとして、1997年9月20日出国~1999年11月16日に帰国するまでの間に訪れた場所を、四半世紀後の私が思い返してみたら、一体何が出てくるのだろうか?という好奇心から古い記憶を辿り、出てきたものを書いてみることを試みたものです。
【ヒンドゥーの数珠】菩提樹の実の|旅の玉手箱 インド雑学編-12
【ヒンドゥーの数珠】
インドのバラナシに滞在中には多くのサドゥー(ヒンドゥー教徒の出家、求道者)を見かけましたが、独特の出で立ちが異様で、初めて見た時はとても気になりました。
すぐに見慣れてしまいその異様さも日常になってしまいましたが、冷静になって考えてみるとインドの異様も普通のような空気感は、楽だったのかもしれません。

私の目からは、インド人は他人の目を気にして生きているようには見えませんでした。
寛容というのか?おおらかというのか?器が大きいというのか?とにかくインドの空気感にはそんな感じがあったように思います。
旅行者の私は物珍しいサドゥーの姿を、興味津々で観察していましたが、独特のファッションが面白くて意外とお洒落にも思っていました。
サドゥーの首には木の実のネックレスが掛かっている姿をよく見かけ、一般のインド人もよく身につけていました。
私は自然素材のものが好きなので、味のある木の実のネックレスに興味が起こり気になっていました。
町を散策していると普通に売っているのも見ましたし、流しで売り歩いている人もいましたので、〈サールナート〉というバラナシ近郊にあるお釈迦様が初めて説法した場所といわれている仏教聖地で、人の善い印象の売人と出会った時に一つ購入しました。

菩提樹(ぼだいじゅ)の実の数珠だそうです。
日本で見かける数珠はネックレスのように長くなく、手に掛けて使用する小さな輪ですが、ヒンドゥー教の数珠はネックレスくらいの長さがありました。
そういえばチベット仏教徒の数珠も長いネックレス程の長さがありました。
説明では108個の実が繋がっているそうで、煩悩の数を表しているそうで、「なるほど」といった具合でした。
ヒンドゥー教も仏教も、古代インドにあったバラモン教から変化した宗教だという流れが感じられます。

売っている新しいネックレスのような菩提樹の数珠は、赤茶けたオレンジに近い色しかなかったので、サドゥーが身に着けているような黒いのが欲しい言ったら、新しいものに黒いものはないんだと教えられました。
長年使用している間に黒ずんでくるのだと。
時々、油を付けて揉んであげるとメンテナンスにもなり、艶と味が出てくるそうです。
「数珠も育ててあげるんだよ」
インドの数珠売りの方の名言でした。
それ以来、旅行中は菩提樹のネックレスを掛け続け、毎日ココナッツオイルで揉み上げましたので、数珠だけは急速に育つこととなりました(笑)
菩提樹の下でお釈迦様は悟りを開きました。

お釈迦様は菩提樹の下で瞑想している時に悟りを開いたそうです。
なので菩提樹は仏教においては聖樹とされています。
インドの〈ブッダ・ガヤ〉の地で悟りを開いたとされ、そこには覚悟の場所に今でも菩提樹が佇んでいました。
ちなみに仏教三大聖樹は、お釈迦様が生まれた場所にあった木「無憂樹(むゆうじゅ)」、悟りを開いた場所にあった木「菩提樹(ぼだいじゅ)」、亡くなった場所にあった木「沙羅双樹(さらそうじゅ)」があります。
HanaAkari