〈日本人〉作品を読んで
 〈日本人〉作品を読んで
〈日本人〉作品を読んで  〈日本人〉作品を読んで
〈日本人〉作品を読んで 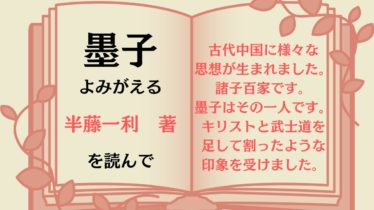 〈日本人〉作品を読んで
〈日本人〉作品を読んで 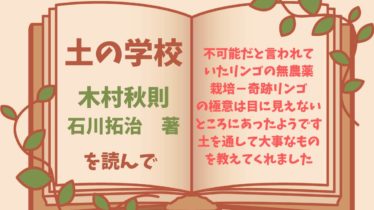 〈日本人〉作品を読んで
〈日本人〉作品を読んで 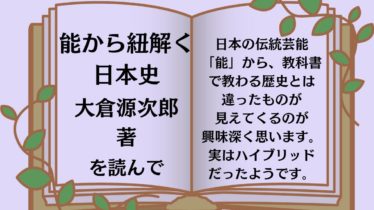 〈日本人〉作品を読んで
〈日本人〉作品を読んで 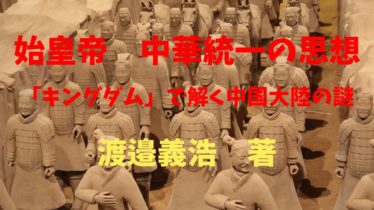 〈日本人〉作品を読んで
〈日本人〉作品を読んで 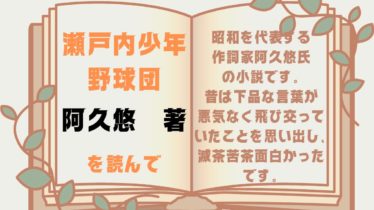 〈日本人〉作品を読んで
〈日本人〉作品を読んで 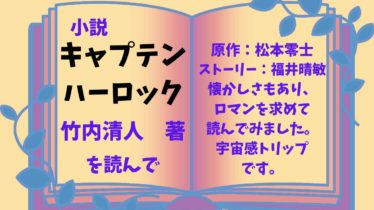 〈日本人〉作品を読んで
〈日本人〉作品を読んで 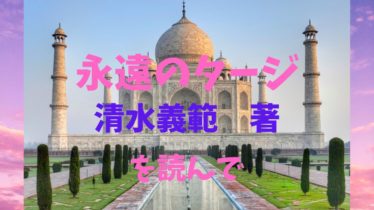 〈日本人〉作品を読んで
〈日本人〉作品を読んで 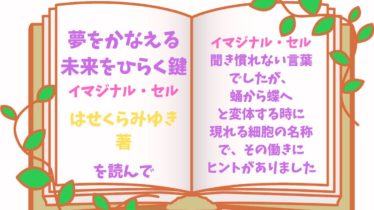 〈日本人〉作品を読んで
〈日本人〉作品を読んで 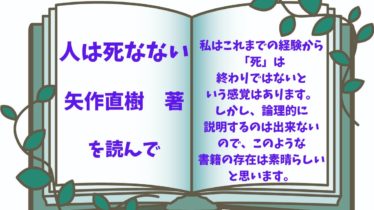 〈日本人〉作品を読んで
〈日本人〉作品を読んで 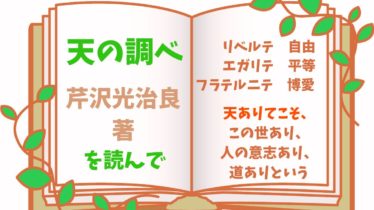 〈日本人〉作品を読んで
〈日本人〉作品を読んで 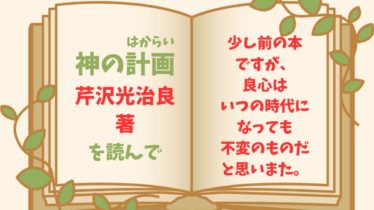 〈日本人〉作品を読んで
〈日本人〉作品を読んで 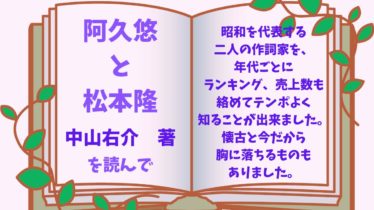 〈日本人〉作品を読んで
〈日本人〉作品を読んで 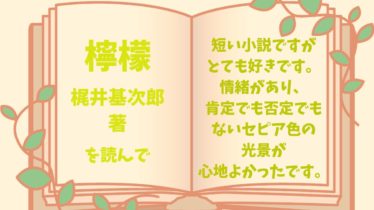 〈日本人〉作品を読んで
〈日本人〉作品を読んで 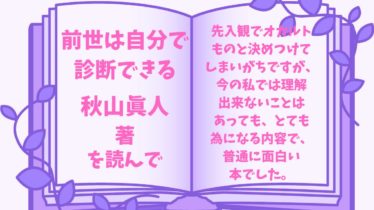 〈日本人〉作品を読んで
〈日本人〉作品を読んで 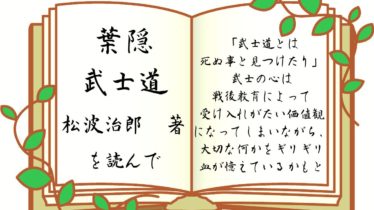 〈日本人〉作品を読んで
〈日本人〉作品を読んで