〈外国人〉作品を読んで
 〈外国人〉作品を読んで
〈外国人〉作品を読んで  〈外国人〉作品を読んで
〈外国人〉作品を読んで 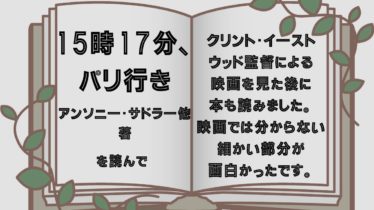 〈外国人〉作品を読んで
〈外国人〉作品を読んで 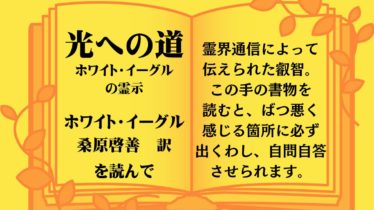 〈外国人〉作品を読んで
〈外国人〉作品を読んで 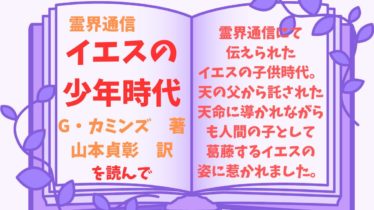 〈外国人〉作品を読んで
〈外国人〉作品を読んで  〈外国人〉作品を読んで
〈外国人〉作品を読んで 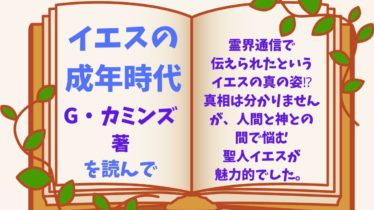 〈外国人〉作品を読んで
〈外国人〉作品を読んで  〈外国人〉作品を読んで
〈外国人〉作品を読んで 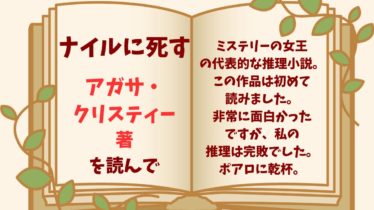 〈外国人〉作品を読んで
〈外国人〉作品を読んで 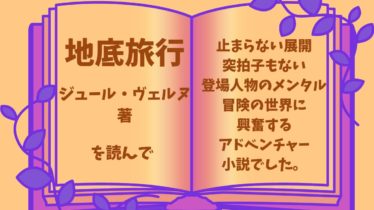 〈外国人〉作品を読んで
〈外国人〉作品を読んで 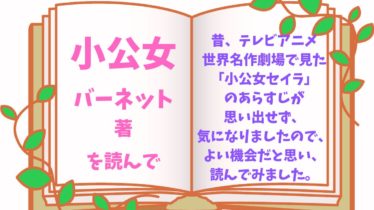 〈外国人〉作品を読んで
〈外国人〉作品を読んで 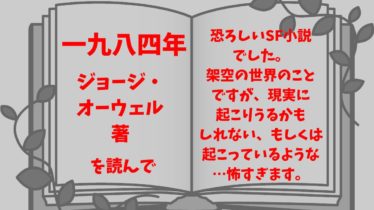 〈外国人〉作品を読んで
〈外国人〉作品を読んで 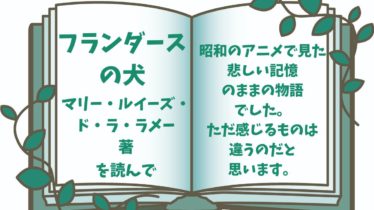 〈外国人〉作品を読んで
〈外国人〉作品を読んで 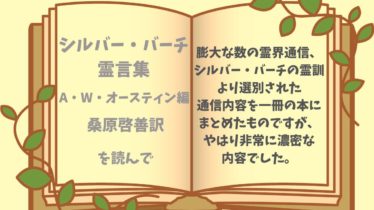 〈外国人〉作品を読んで
〈外国人〉作品を読んで 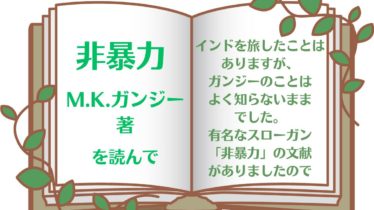 〈外国人〉作品を読んで
〈外国人〉作品を読んで 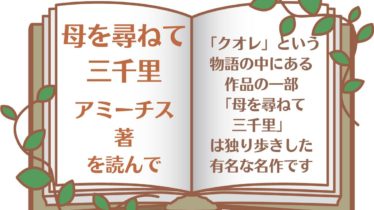 〈外国人〉作品を読んで
〈外国人〉作品を読んで 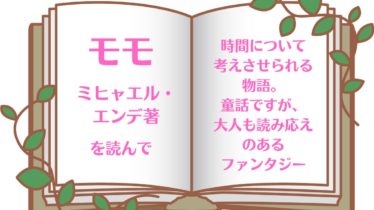 〈外国人〉作品を読んで
〈外国人〉作品を読んで