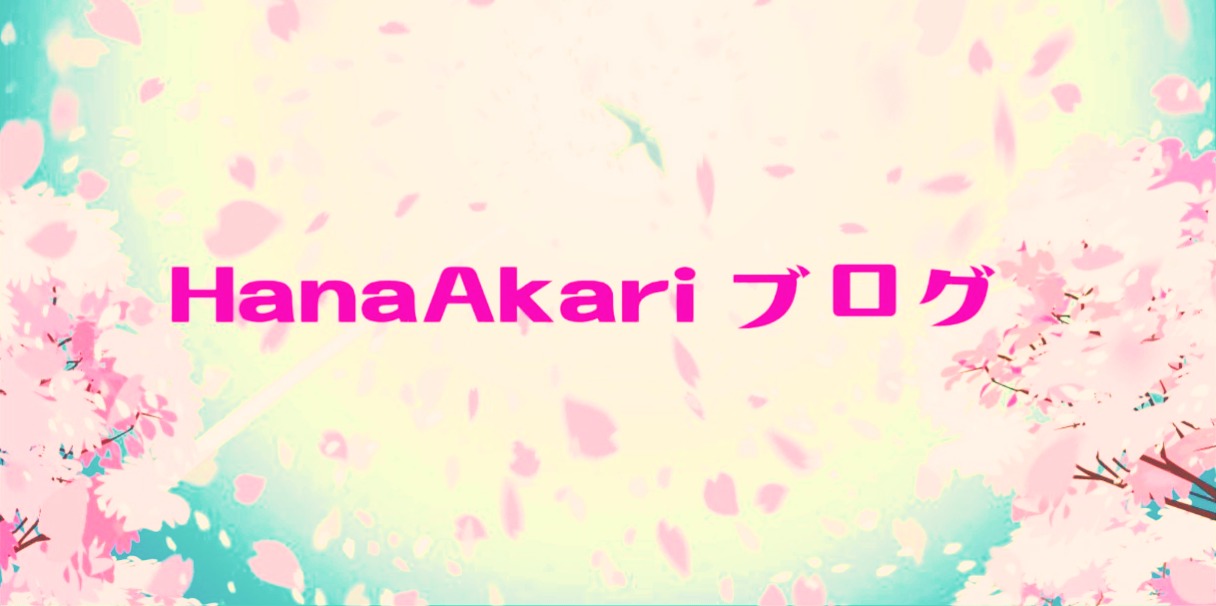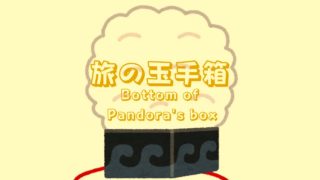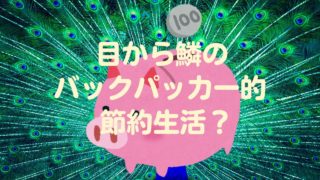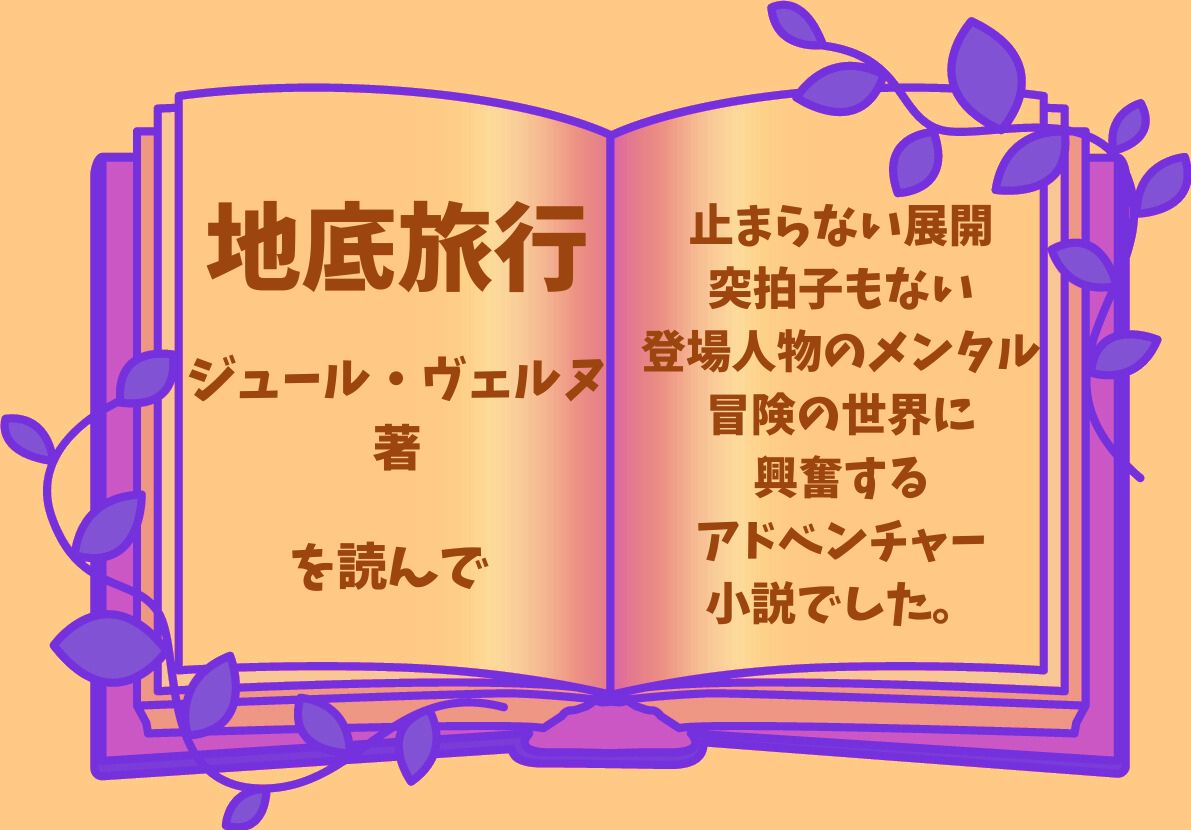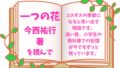傍若無人な教授と真面目な弟子、寡黙に淡々と仕事をこなすガイドの三人が地底世界を冒険する物語。スピーディーな展開にいつしか前のめりになって読んでいました。
冒険小説のお手本のような物語でした。
途轍もない独断専行型の〈リーデンブロック教授〉に牽引されて、地底の底にある世界を目指す物語ですが、走り出したら止まらない勢いに、いつしか前のめりになっている自分が可笑しかったです。
現実にはありえないような冒険なのに、実際に冒険の旅をしているかのような気持ちになってしまうのは、私のような影響を受けやすい人間の特技かもしれません。
カンフー映画を観た後に、自分もカンフーの達人になった気分になっているのと同じような現象がありました。

物語は〈リーデンブロック教授〉の弟子であり甥でもある、〈アクセル〉の日記形式で語られているのが面白さを引き立てていました。
〈アクセル〉は極めて一般的な感覚を持つ真面目な青年で、いわゆる常識人なのですが、叔父の〈リーデンブロック教授〉の豪胆な傍若無人ぶりに対しての溜息交じりの感想が、私も同感なのですが、傍から見ている分には笑えてしまいました。
おそらく〈アクセル〉の言動が面白いのではなく、〈リーデンブロック教授〉のぶっ飛んだ言動が、有り得ないと思いながらも痛快すぎるのだと思います。
〈リーデンブロック教授〉は冒険に向かう前から最後まで終始一貫して、恐るべき人物のまま途轍もない行動力を見せてくれました。
数々の吹き出すエピソードがありましたが、中でも本当に笑いが噴き出した箇所があります。
地底世界への入り口がある火山の噴火口の底から、いよいよ地底に向かう穴を目の前にして、さあ、どうやって荷物を運ぼうかと思案する〈アクセル〉の目の前で、〈リーデンブロック教授〉は荷物の大半を底が見えない穴の中に投げ入れて、こう言い放ったのです。
「さて、わたしたちの番だ」と。
〈アクセル〉はこう綴っていました。
「僕はすべての率直な人にうかがいたい、このような叔父の言葉を聞いて、身震いせずにいられるものかを!」
当事者なら当然身震いするところですが、読者の立場からすると面白すぎる場面でした。
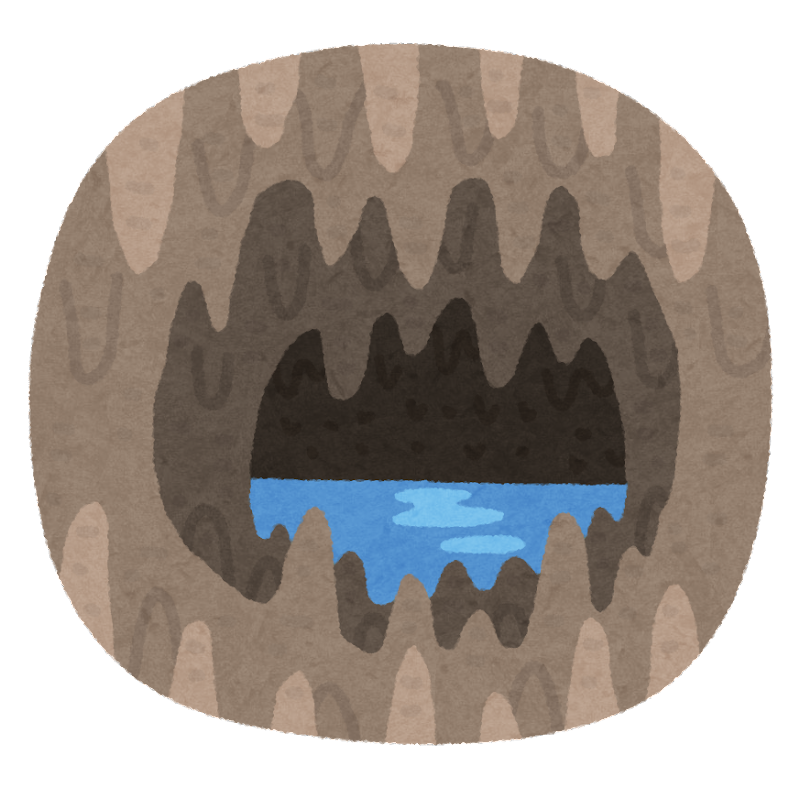
またこのとんでもない冒険には、一人のガイドが雇われて同行するのですが、このガイドの〈ハンス〉が独特の魅力を発揮しているのも見どころでした。
非常に優秀でどんな状況でも黙々と仕事をこなして大活躍し、淡々とお給料を受け取るのです。
何が起ころうとも引き受けた仕事はこなすのが務めだということを、行動で示す能面みたいな男でした。
鋭い感覚に傍若無人な豪胆さ、猛禽類のような〈リーデンブロック教授〉と、いたって真面目な常識人の〈アクセル〉、傭兵のごとく仕事をこなす寡黙な能面ガイドの〈ハンス〉の三人組のチームが最高でした。
この三人だからこそ奇想天外な地底旅行から、運も味方に付けて帰還できたのでしょう、きっと。
名言「人間が想像できることは、人間が必ず実現できる」〈ジュール・ヴェルヌ〉
私は〈ジュール・ヴェルヌ〉氏の作品が好きで、子供の頃は夢中になって読んだものでした。
1825年2月8日~1905年3月24日を生きた、フランス人の作家です。
冒険や当時は空想だった科学的要素を盛り込んだ小説には、非常にワクワクしたものです。
「人間が想像できることは、人間が必ず実現できる」
〈ジュール・ヴェルヌ〉の名言です。
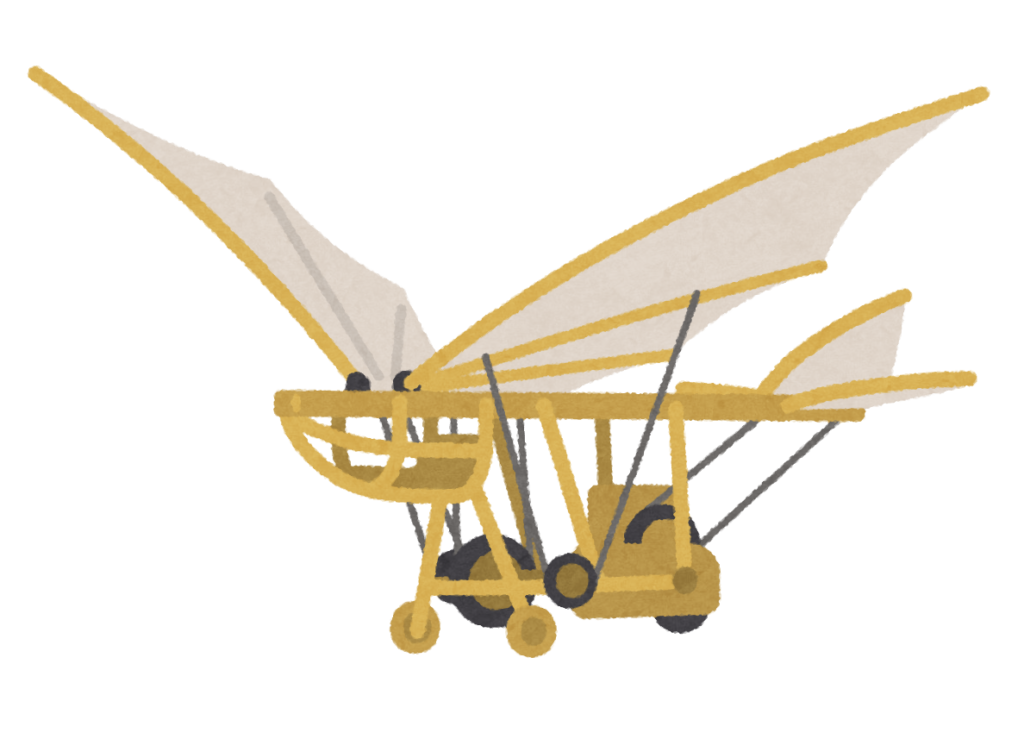
HanaAkari