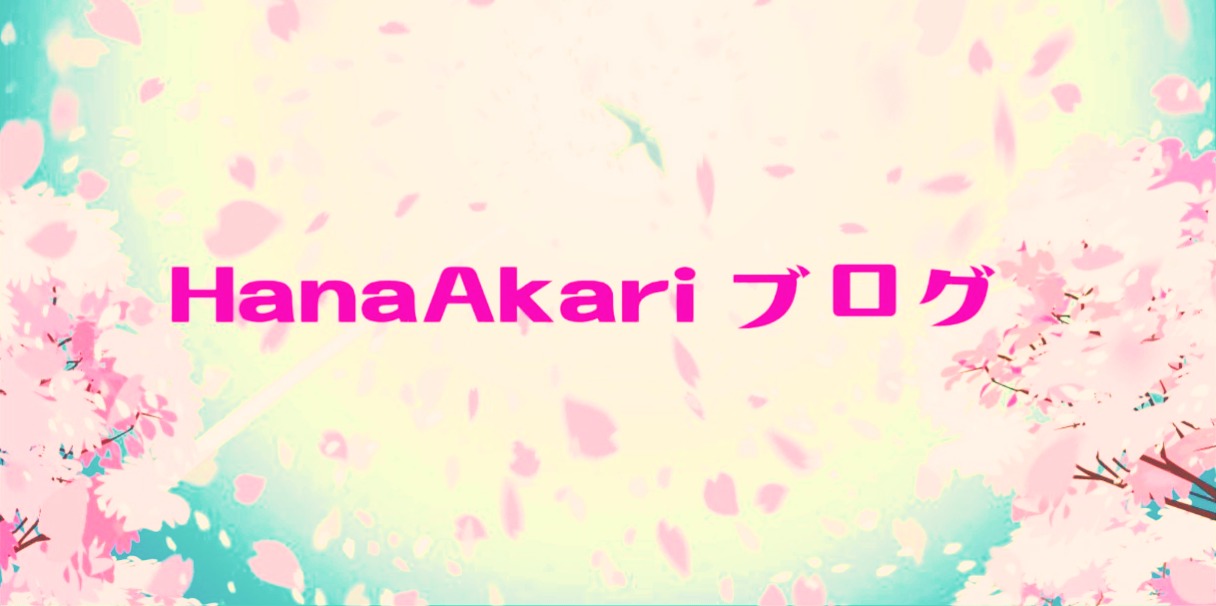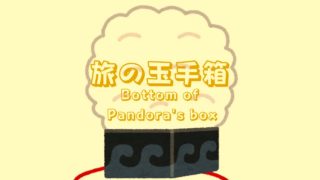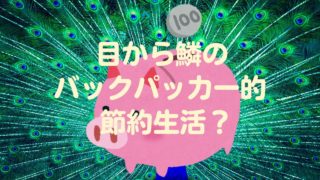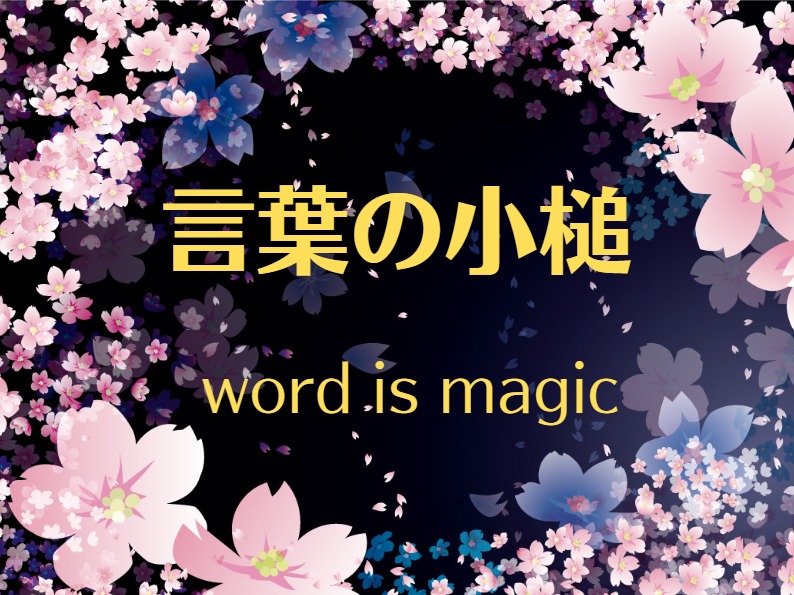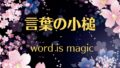「花の谷という魅力的な響きと、近くにはヘームクンドと呼ばれるシーク教徒(男性信者は頭にターバンを巻いている)の聖地まであるらしいことが分かり、「聖地」となると宗教や人種や国など関係なく目がキラキラしてしまう質ですので、行くか?行くまいか?と本当に悩んだ末に諦めたのでした」
「谷一面に花が咲き乱れ、小鳥のさえずりと輝く水面、優しく太陽の光が降り注ぎ、爽やかな風が吹き抜ける、そして花の精は踊り出すといった世界を想像してしまいます」
このブログは言葉から連想したことを自由に書いています。時に勇気や喜びをもらえたり、慰められたり、癒されたり、言葉には力があるように思います。そんな素敵さや楽しさを少しでも表現できたら幸いです。
【花の谷】インドの国立公園とシーク教徒の聖地は夢|言葉の小槌12
【花の谷 Volley of Flowers】
「花の谷」という響きにはそそられます。
まだ20世紀の頃に私がインドを旅行していた時に、携えていた持ち物の中には「地球の歩き方 インド」と英語の「Lonely Planet India」という当時バックパッカー御用達のガイドブックがありました。
「地球の歩き方」は日本語ですので一番使いやすかったのですが、有名でない場所や辺境に行くには情報量が少なかったので、時には分からない英語に苦戦しながらも「Lonely Planet India」からの情報を参考にしました。
自由で特に目的地を定めている旅ではなかったので、知り合った旅行者からの生の情報を参考にすることが多かったですが、ガイドブックと照らし合わせて旅の計画を練る時間も楽しかったです。
私はあまのじゃくなところがあったので、あまり大勢の旅行者が訪れるような所よりも外国人旅行者があまり行かない所を好んで行く傾向がありましたので、英語はよく分からないながら「Lonely Planet India」には結構目を通していました。
「Volley of Flowers」「花の谷」というフレーズを見つけたのはその時で、即座に行ってみたいと思い、調べてみて悩むことになりました。
かなりの僻地であり山登りあり、行って帰ってくるには日数もかかる上、花が咲くある一定の時期に予定を合わせないといけないことで、他に行きたい所との兼ね合いがうまく付かないのですが、「花の谷」という魅力的な響きと、近くにはヘームクンドと呼ばれるシーク教徒(男性は頭にターバンを巻いている)の聖地まであるらしいことが分かり、「聖地」となると宗教や人種や国など関係なく目がキラキラしてしまう質ですので、行くか?行くまいか?と本当に悩んだ末に諦めたのでした。
その分「花の谷」へ対する空想は広がり、「聖地」という言葉と結びついて、おそらく「天国」「楽園」のようなところではないだろうか?谷一面に花が咲き乱れ、小鳥のさえずりと輝く水面、優しく太陽の光が降り注ぎ、爽やかな風が吹き抜ける、そして花の精は踊り出すといった世界を想像してしまいます。

ちなみにインド人といえばターバンを巻いているイメージが強かったのですが、大半のインド人はターバンを巻いておらず、インド人=ターバンのイメージは刷り込まれた思い込みでした。
ターバンはインド人の中でもシーク教徒だけの風習とのことで、戒律で男性は髪や髭を切ってはいけないらしく、ターバンには長い髪を束ねる役割があるそうです。
大半のインド人はヒンドゥー教徒で次にイスラム教徒がいるといった具合ですので、実際はターバンを巻いている人の割合は少ないのです。
花の谷のHanaAkari