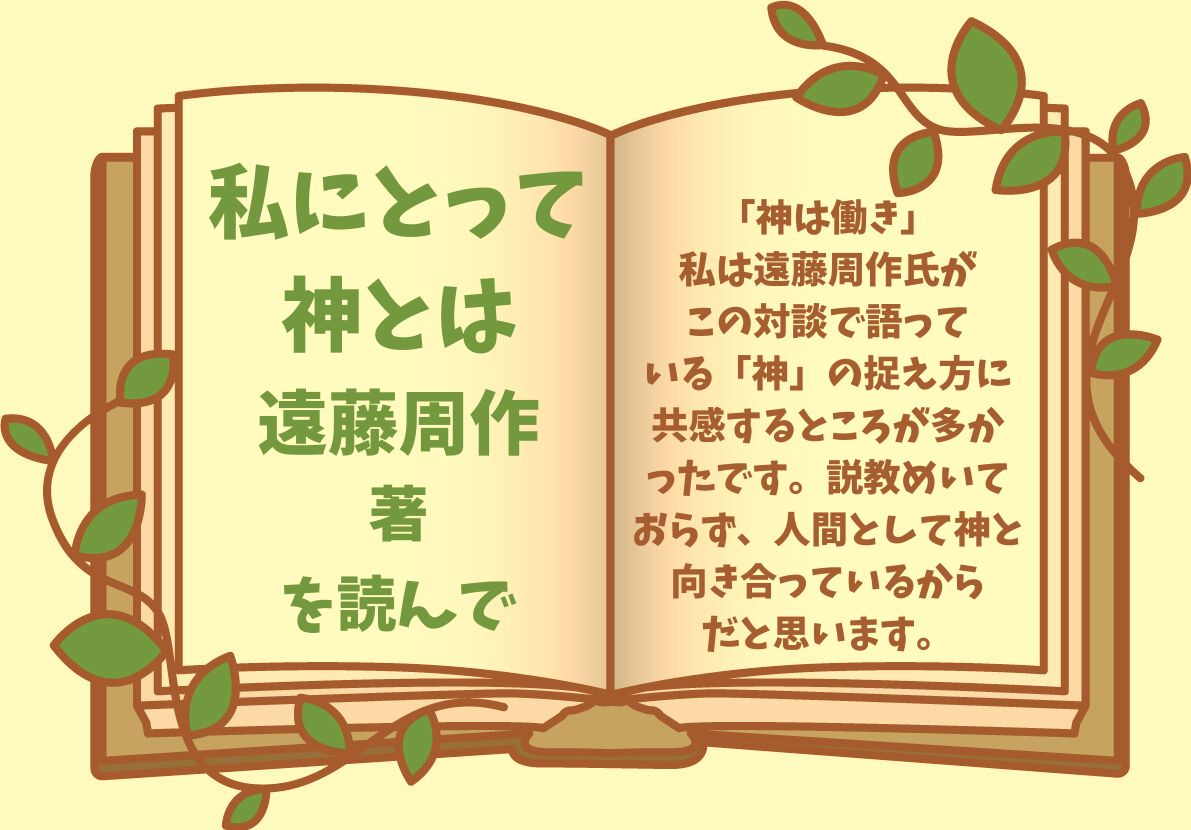遠藤周作氏は「神」のことを働きと表現されていました。
私はこの本を読んで、遠藤周作氏の作品に感じる面白さや魅力の源泉を知れたように思います。
かくあるべきだという宗教に見られがちな観点からではなく、物書きとして一人の人間から語っているので非常に親近感があり、気色の悪さを感じたり拒絶反応が起こらずに読み進めることが出来ます。
綺麗ごとだけにとどまらない、泥にまみれた汗臭さがあるのである意味、真面目な「神」や「信仰」から落第した私のような人間にも読めるのだと思います。
また非常に共感する部分も多くありました。
「神というものは対象ではなく、その人の人生の中で、その人の人生を通して働くものだ」この表現には震えるものがありました。
背中を後ろから押してくれている働きであって存在ではないと。
遠藤周作氏がキリスト教と縁を持った経緯から、信仰を諦めかけたこと、神と自分との葛藤など、この本には格好をつけずに本音が語られているので、歯切れがよくて気持ち良かったです。
何が正解なのかは分かりませんが、遠藤周作氏流に表現すると、彼の書いた本が私の人生を通り過ぎたことで、何かしらの痕跡を残したのでしょう。
働きがあったということになるのだと思います。

神を恨むところから本当の宗教が始まる?
とても気になった表現に「本当の宗教というのは、神も仏もあったものかと思ったところから出発するのではないのだろうか?」というものがありました。
人は神に絶望したり、恨んだり、神も仏もあったものじゃないと怒りを感じることがあった時から、初めて真摯に神と向き合えると言っているのでしょう。
面白いと思いました。

聖書の一文に「汝は冷たくもあらず、熱くもあらず、ただなまぬるきなり」という言葉があるそうです。
人生でなまぬるいやつは神を知らない、だから、激しく神を愛するか、激しく憎むか、そのどっちか・・・つまり本当の無神論者ならば神を知ることができる…
神などあってもなくてもどっちでもいいというような人には、永久に神はわからないだろう…
聖書を直接読んでも退屈で何が何だかさっぱりな私ですが、遠藤周作氏を通してでしたら興味をそそられます。
HanaAkari