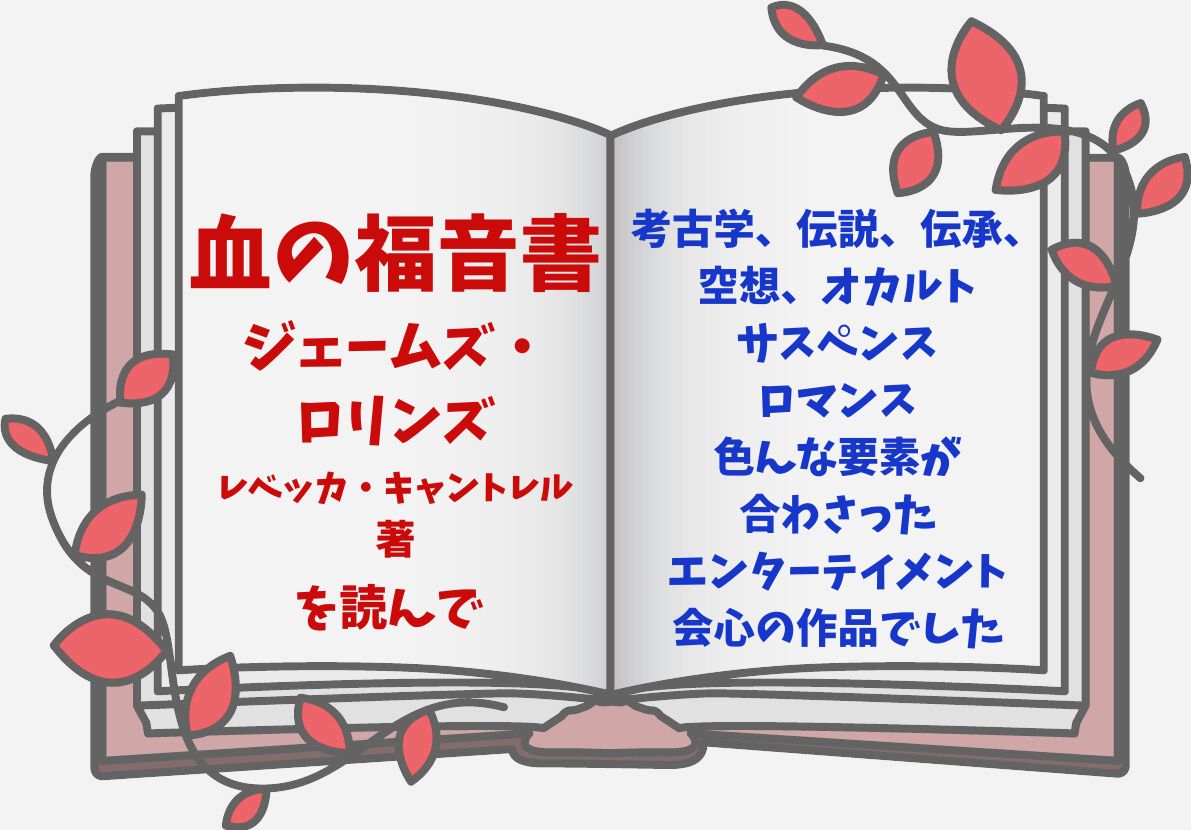聖書においてワインは血、血といえば吸血鬼。想像考古学の世界「血の福音書」上巻
非常に面白い演出と世界観、史実と空想の間に魅了され、知らず知らずのうちに読み進めていました。
イスラエルの死海のほとりに切り立った岩山、悲劇に血塗られた遺跡「マサダ」から物語が始まりました。
「マサダ」は大国ローマの軍に追い詰めれたユダヤの民が最後に立て籠もった天然の岩山の要塞で、追い詰め包囲したものの、ローマ軍は攻めあぐねてしまいます。
天然の要塞「マサダ」を陥落されることが出来ないローマ軍は、二年の歳月をかけ断崖を埋め立てて突破口を作り、攻略したという歴史があります。
そして追い詰められたユダヤの人々は、集団自決をした場所です。
この歴史の話が頭の片隅にあったので、この「血の福音書」の世界に、一気に前のめりになってしまいました。
考古学を題材にした冒険物語としては、「インディー・ジョーンズ」に近いのですが、「血の福音書」はもっとオカルト色が濃いので、私のようにオカルト好き向きなのかもしれません。
この物語には初めて知る形態で吸血鬼が登場するのですが、吸血鬼、ゾンビ、マミーなどは、恐怖を感じるけれども、怖いもの見たさの対象としては上位にのぼる存在です。

語弊を恐れずに言うと、神も悪魔も宗教もオカルトも全て紙一重のような違いしかないように思いますので、神秘的な要素が詰め込まれたこの作品はその部分だけをとっても興味深いものでした。
その謎めいた歴史的背景を舞台に、陰謀、裏切り、謀略などのサスペンスがあり、ドンパチ、戦い、さらにはロマンス要素が組み合わさっているので、人が興味を惹かれるもので目白押しなのが堪りません。
また、時折ハッとさせられたり、思わず胸に手を当てて考えさせられるような文面が出てくるので、何層にも楽しいのです。
考古学者のエリンの言葉にこのようなところがありました。
「考古学では聖書は常に…起こった出来事の宗教的な解釈ととらえるべき」だと。
「宗教的な意図を持つものが、自分たちの思想に沿うよう、事実を歪曲して記したもの」
「神聖なものが存在するとしたら、それは聖書のなかにあるものではないわ。神聖さは男性、女性、それに子ども、それぞれの心のなかにあるものよ。教会にあるものではないし、神父の口から出てくるものでもない」

考古学者エリンはとても魅力のある存在で、強烈なオーラを放っていました。
エリンは血にまみれた隠された裏の世界に巻き込まれていくのですが…
また裏の世界の者にとっては、血にまみれた道が生きる場所であり、普通の人間の平凡な世界は生きているとはいえないというような記述がありました。
「普通の人間はこの世界の真の姿に気づきもせずなんと安穏と暮らしているのだろう。規制され、選別されたニュースが二十四時間休みなしに流れる、安全で便利な生活にどっぷり浸かり、カフェインの力を借りて、目をしょぼしょぼさせながら平凡な一日を送っている」
私はこの一文の中にある、平凡こそが幸福の原点ではないかと感じますので、血生臭い発想は物語の中のエンターテイメントだけであってもらいたいと思いました。
大きな業を背負った聖職者であり、教会の戦士でもあるルーンは吸血鬼でもあるので、彼の葛藤の声にはとても辛いものがありました。
そしてその言葉には、悲哀が幾重にも沈殿し重みがありました。
聖品、十字架は闇のものに対しては武器にもなるようですが、ルーンはこう発言しました。
「単なる武器ではない、キリストのシンボル、武器を超えたものだ」と。

十字架を背負った人々が悲劇の血にまみれる。想像考古学の世界「血の福音書」下巻
著名な歴史家の中には、その知識を後世に残すことなく墓へと持っていった者も多い。
「血の福音書」は、時にはその方が良かったのではないかと思えるような展開になっていくのが、若干辛いところでした。
業を背負った吸血鬼ルーンやその仲間がキリストの赦しを得る代わりに、誓約と血の誘惑との間で苦しむ姿がいたたまれません。
人の生き血を吸う代わりに、清められたワインで生きるようですが、残酷にもワインを口にすると業の深さの分、辛い過去の罪と向き合うことになり、体は不死なだけに心はずっと痛めつけられてしまう。

不死ゆえの吸血鬼の本能は、人間が血の雫を床に一滴落とす音すらも、大きな雨粒が薄い金属でできた屋根を打つ程に響き、血を欲する肉体と闘わないといけない。
「サンギニスト」と呼ばれる吸血鬼たちの葛藤は計り知れないものがありそうでした。
不死は祝福の証ではない。
呪いだ。
そのような文面もありました。
それ程に過酷な節制の中で、神の戦士として生きる「サンギニスト」ではあるものの、人間の戦士ジョーダンにとっては、全面的には気の許せない警戒する存在になり、そこに心を寄せるエリンが絡んでくればなおさらそうで、それによって嫉妬や怒りの感情と向き合わざるを得ない展開も当然の成り行きなのでしょう…
人も吸血鬼も、自分の心と向き合うのが一番の苦痛なのだと…胸が痛くなりました。

冒険の途中に「サンギニスト」を破門にされた重要人物らしき者が、本能に従って生きることをルーンに問いかける場面には注視せざるを得ないセリフがありました。
「結局、われわれは自分自身以外ではありえないのだよ、ルーン。運命と闘うのではなく受け入れれば、想像もしなかった強大な力を手にすることができる」
それに対して神の御心と共に生きようとするルーンの返答がこうでした。
「わたしは力など求めていない。わたしが求めているのは神の恩寵だけだ」
それに対して「もう何百年も生きてきたというのに、まだその恩寵とやらは見つからないのか?もしかすると恩寵は教会の壁のなかではなく、自分の心のなかにあるのかもしれんぞ」
こういう哲学的展開がやってくると、どちらにも一理あるようでお手上げになってしまいます。
「あなたはどっち?」と尋ねられても答えが出せず、降参するしかないですね。
今の私はグレーゾーンで保留しておくしかないようです。
私は、この物語の中でルーンの心のあり方、迷いや葛藤に非常に興味を持つことが多くありました。
そんなルーンの心が率直に現れている場面を抜粋して終わりたいと思います。
呪われた人生を生きる怪物の身ながらも、この世界のために真に偉大なものを手にすることができた。あるいはこの福音書に、ルーンがみずからの魂を取り戻す方法が記されているかもしれない。そんな虫のいいことを考えてしまう自分や、他人と分かちあうべき鼓動とあたたかな肌を持つ人間に戻りたいと願ってしまう自分の弱い心が恐ろしくもあった。
「血の福音書 下巻」より
HanaAkari