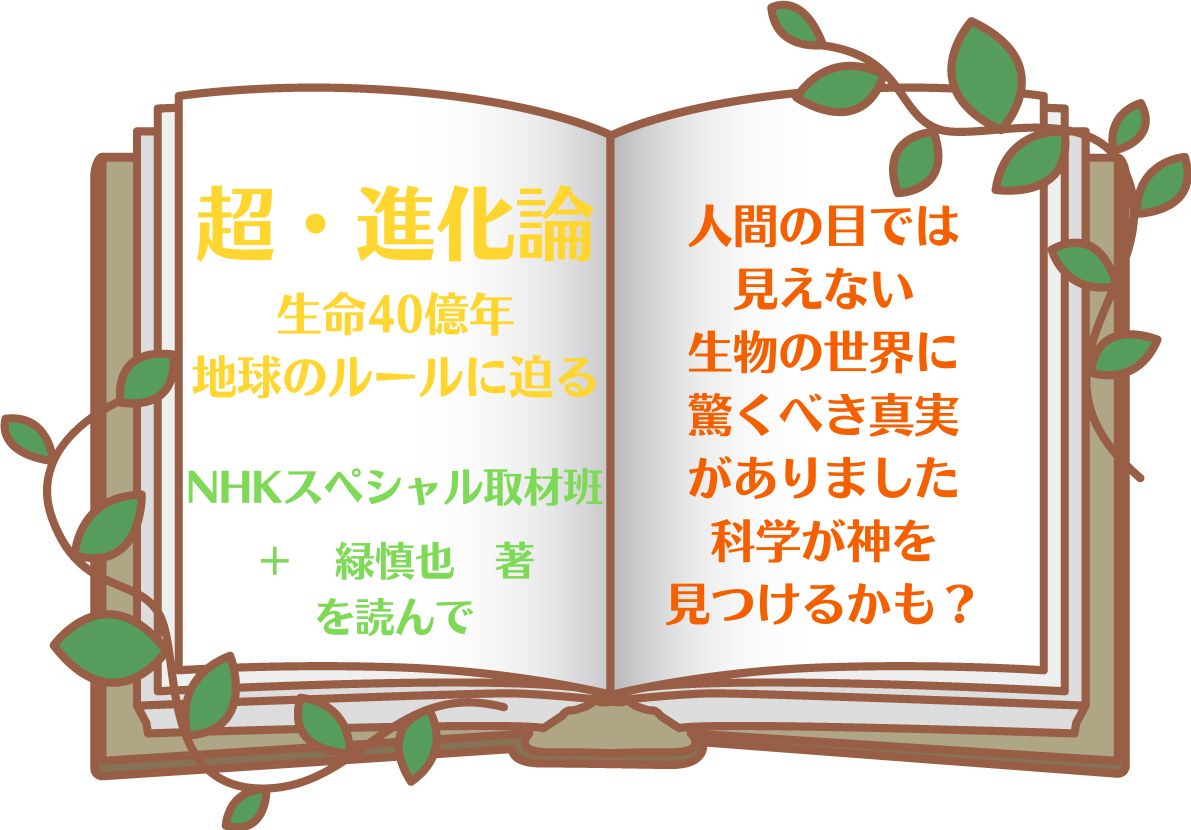「共生」が答えかもしれません。小さな世界には偉大な知恵と神秘が詰まっているようです。
目に見えないものを信じない傾向は、どうしてもあると思います。
私も少しは目に見えないことも受け入れるようにはなりましたが、なかなか素直に全てを受け入れる程にはなれません。
しかし、科学の進歩でこれまでは見ることが出来なかった世界や、これまでは紐解くことが出来ず、予想するのも難しかったことがどんどん発見され、今までの常識を覆してくれることも多くなりました。
「超・進化論|生命40億年 地球のルールに迫る」はそのような本でした。
人はどうしても自分の視点から物事を考えるのが癖になっているので、見誤ることが多くなるのも仕方がないことかもしれません。
「植物が植物同士で話をしている」なんて言われても、「そんな馬鹿な」と思うのが普通の反応でしょう。
「喋れない植物が話が出来る訳がない」そんな思考が真っ先に起こってしまうのは、とてももったいないことなのだと、「超・進化論|生命40億年 地球のルールに迫る」は教えてくれました。

科学的に証明されている結果ですから、迷信や思い込みでない分受け入れやすいですが、いざ蓋を開けてみると人間よりも下等生物だと思っていた動植物の方が、進んでいるようでした。
地球の覇者は「裸の王様」だったのだと教えてくれているようでした。
植物は会話している、感じている、種類の違う植物同士でも協力し合って生きている。
虫ともうまく共存している、さらには生物はすべからく微生物と共生していて、微生物なしでは生きられない。
結局はすべて繋がっていて、必要不可欠なのだ、そんな風にしか思えませんでした。
見る位置や角度、立場の違いから良い悪いがあるのだろうけど、浅はかな猿知恵で悪いと決めつけて排除したり、駆逐しようとする行為は自然の秩序を乱し、最終的には我が身に跳ね返ってくるのだというのが、可視化されてきたのは幸いかもしれません。
科学が神を証明することにもなるのかもしれないと思えます。
科学が神を越えるいうことではなく、神の存在を明らかにして、さらなる無限さに畏怖するのでしょう。
畏み畏み申しますです。

映画「アルマゲドン」を思い起こさせる植物の記述がありました。
「超・進化論|生命40億年 地球のルールに迫る」には、これまで知らなかったことが多くあり、「渡り鳥」ならぬ、「渡り虫」がいることを知ったり、非常に楽しい新常識が満載で面白かったです。
中でも私が特に印象に残った記述は、ある植物のことでした。
植物は化学物質を使ってコミュニケーションを取り合っているそうですが、山火事になった時に焼けた植物が出す煙に混じっている化学物質に反応して、芽吹く草木があるそうです。
他の条件下ではほとんど発芽せず、土の中で眠っているのですが、「カリキン」という化学物質を含む煙にさらされると一気に目覚めるというのです。

火事になっても走って逃げることが出来ない木々は、自分の命はそこで一旦尽きるのだけど、その焼け野原になった大地に、次の新たな生命のためにバトンタッチの呼び掛けをしているように感じました。
灼熱の過酷な焼け野原に新たに育っていく者たちに対して、愛があるみたいです。
繋げていく。
託されたものはその思いを大切にして、精一杯生きる。
そのように想像しました。
映画「アルマゲドン」の最後に一人の宇宙飛行士が、命を投げだして人類を救うシーンがありましたが、その情景と重なり合うのでした。
エアロスミスの「Miss a Thing」が流れてきました。
これまでは自己犠牲が美しい感動映画のように思っていたのですが、もしかしたら犠牲という言葉は適切でないのかもしれません。
「愛」
以上です…
ただ、心は映画のように簡単には納得できず、悲しみが和らぐまでは「愛」だと感じることが難しいのが、人の人たる所以なのかもしれません。
HanaAkari