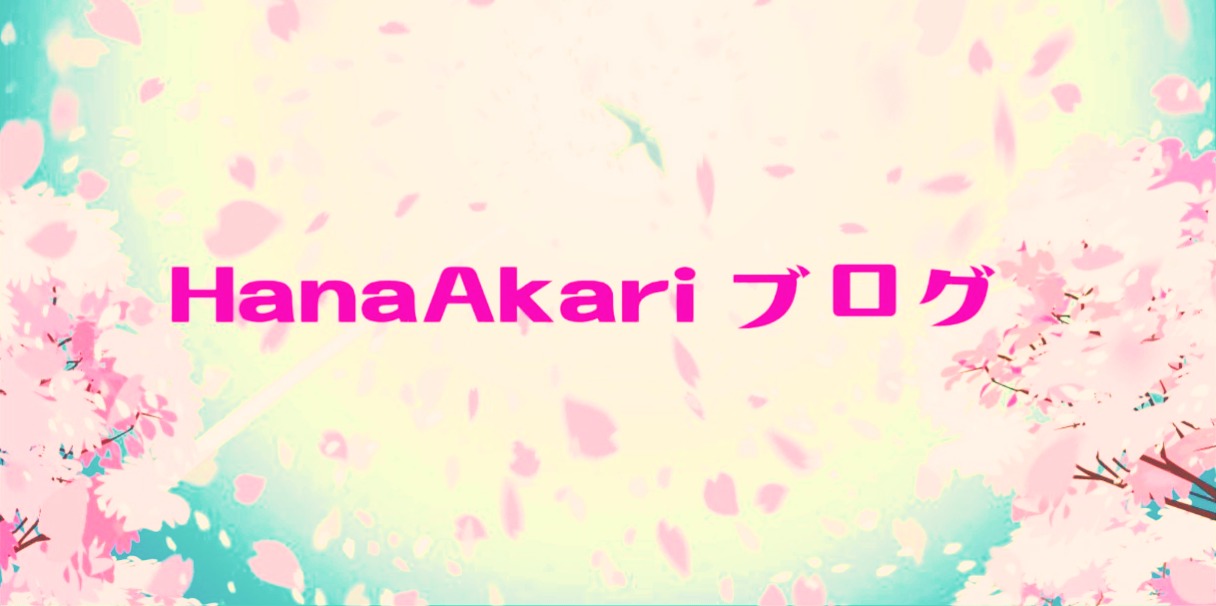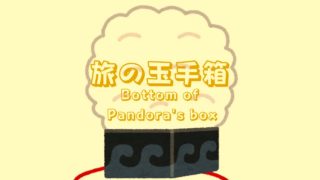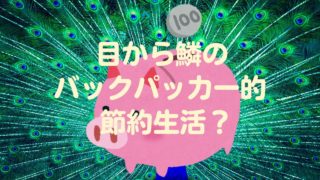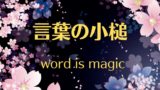このブログは私がバックパッカーとして、1997年9月20日出国~1999年11月16日に帰国するまでの間に訪れた場所を、四半世紀後の私が思い返してみたら、一体何が出てくるのだろうか?という好奇心から古い記憶を辿り、出てきたものを書いてみることを試みたものです。
【水上バス】バンコクの川と運河の情景|旅の玉手箱 乗り物編-8
【水上バス】
初めてタイのバンコクに行った時に、一度だけ運河を縫うように運行されていた、小舟の「水上バス」を利用しました。
狭い運河をかなりのスピードで、決められた船着き場を経由しながら、乗客を乗せたり降ろしたりしながら、せからしく運行されていました。
のんびりと運河を進んで行くのではなく、モーターエンジン全開で、猛スピードで運河をジグザクに行きました。
船着き場は水路の片側にあるのではなく、対岸にもありますので、大抵ジグザグに行き、時々フェイントで同じ側に連続して止まってりしました。
人の乗り降りの際も、のんびりしていません。
せわしく人の乗り降りを済ませては、一分一秒を争うかのようにフライイング気味で動き出しました。
運河を上手く活用した生活は、なかなかいいもののように感じました。
私は大阪に住んでいますが、水都大阪と呼ばれたり、江戸時代には八百八橋とも謡われたりしたものの、堀は埋め立てられて道になった所が多く、今では残念ながら水都というイメージはあまりありません。
バンコクには勝手ながら、水の文化を上手に維持していってもらいたく思います。

バンコク市内を流れる「チャオプラヤー川」にも、一見すると渡船のような「水上バス」が運行されていました。
バックパッカーが集まるバンコクの安宿街カオサンロードの近くに、チャオプラヤー川を行き来する「水上バス」の船着き場がありました。
これがタイの三大寺院観光に行くのに使い勝手がよく、川の文化を楽しめて、私はとても好きでした。
こちらも主にジグザク運行しますが、時にフェイントで対岸に行かないこともありました。
このカオサンロード近くの船着き場から行った観光場所を、思い起こしてみようと思います。

シリラート病院の「死体博物館」は忘れたい記憶のようです。
カオサンロード側からすると少し下流の対岸にある「シリラート病院」には「死体博物館」があり、観光地として有名でしたので、行ってみたのですが、正直あまり気持ちの良い場所ではなかったです。
かなり精神的に厳しいと言った方が適格でしょう。
資料として保存しているのでしょうが、ホルマリン漬けされた死体やミイラをたくさん見ても感動はしませんでしたし、異形の人間のホルマリン漬けもあったのはなんとなく憶えていますが、映像は出てこないので、自然と忘れるように私の中で記憶操作が、行われているのだと思います。
何でも経験だと思って、なんでもかんでも観光すれば良いということではないのかもしれないと、思うような場所でした。
「ワット・プラケオ(エメラルド寺院)」の参道が、良かったです。

シリラート病院からもう少し下流に行った、カオサンロード側には「ワット・プラキオ(エメラルド寺院)」があります。
タイ語で「ワット」=「寺」ですので、「ワット・何々」とあれば、「何々寺」ということになります。
「ワット・プラケオ」は「プラケオ寺」ですね。
あの頃、私は仏教を始め、宗教や精神世界のことなどには一切興味が無かったので、お寺の観光をしても、「造りが独特で派手な建造物だなぁ」「それにしても暑いなあ~」と思うくらいで、特に真剣に見て回らなかったのは、もったいなかったと今では思います。
私がタイの寺で印象深かったのは、タイの人は日常的にお寺に参拝しているようだったのを不思議な気持ちで眺めていたことと、真剣にお祈りする人々の姿が気になり、感動している自分自身が意外だったことです。
タイの人々は参拝する時に、蓮の花のつぼみをお供えしていたのですが、その行為と蓮の花のつぼみがとても私の心に響きました。
なぜだかは分かりませんが、蓮の花のつぼみに強く惹きつけられたです。
このことについて軽く触れた記事、「言葉の小槌24 蓮華」もありますので、もしよければそちらも読んでみて下さい。
あと、船着き場から寺院までの参道沿いには屋台が並んでいて、土産物や食べ物が売られていたのが楽しかったです。
スルメイカがとても美味しかったです。
一匹を丸々干した状態のスルメイカでした。
味は日本のものと変わらないか、むしろタイの方が味が濃くて美味しいような気がしましたが、旅先でのことなので、いろんなことに対しての採点は、大判振る舞いになっているかもしれません。
知り合ったイギリス人は「臭いから食べることができない、不味い」と言っていましたが、韓国人の友人とは、「この匂いが美味しいのに」と意見が一致したりと、文化って様々で面白いと思います。
「ワット・ポー(涅槃寺)」の巨大な黄金の寝釈迦仏は、見ごたえがありました。
ワット・プラケオからさらに下流に少し行くと、黄金の巨大な寝釈迦仏で有名な「ワット・ポー」があります。
こちらは圧巻の巨大な黄金の寝釈迦仏が迫力があり、単純に観光のしがいがありました。
「涅槃仏」とも表現され、お釈迦様の死を表現しています。
「北枕」で寝ると縁起が悪いと言われるのは、お釈迦差が北側に頭を向けて亡くなったことから連想されているようですが、風水では「北枕」は良いなんて言われますので、謎です。
「ワット・ポー」はタイ式マッサージの総本山でもありますから、実際にタイ式マッサージの施術を受けることもできますし、タイ式マッサージを習うこともできます。
バックパッカーの中にもここでタイ式マッサージを習い、免状を取得する人が多くいました。

「ワット・アルン(暁の寺)」には対岸からのみの観光になりました。
ワット・ポーの対岸には「ワット・アルン(暁の寺)」がありましたが、実際に現地には行きませんでした。
熱心に観光していると蒸し暑さで、疲れが出てきてワット・ポーの次に行こうかと考えていた、「ワット・アルン」は諦めることにしました。
ただチャオプラヤー川を挟んだ向こう岸に、堂々と建つ姿は十分に見ごたえのあるものだったので、満足しましたし、何より休息が必要でした。
その時の状況で好きに予定を変更できるのは、バックパッカーの自由気ままな旅のいいところだったと思います。

「タマサート大学」には学食を食べに何度か行きました。
カオサンロード側の少し下流にある、「タマサート大学」には、水上バスで行ったり、近いので時には歩いても行きました。
目的は学食でランチを食べることで、安くて量が食べられるのが嬉しいことでした。
バンコクの「水上バス」のことを思い出していて、残念なことに気が付きました。
「水上バス」を使って観光できたことはとてもいい思い出ですが、一つだけ残念なことがあります。
それは下流側にも上流側にも終点まで行かなかったことです。
今なら特に目的地はなくても、やってみると思うのですが、あの頃は観光することに焦点があり、ただ終点にまで行ってみるような、時間の無駄使いのような行為をしなかったことが惜しまれます。
私はなぜかそのような事が好きで、目的が終点に行くことのみで、その間にぼんやりと景色を眺めたり、考え事したり、到着した先で行き当たりばったり歩いてみたりするだけのことなのですが…
なぜあの時、気が付かなかったのかと、少し悔やまれす。
もしも次にバンコクに行くことがあれば、是非やってみようと思います。
HanaAkari