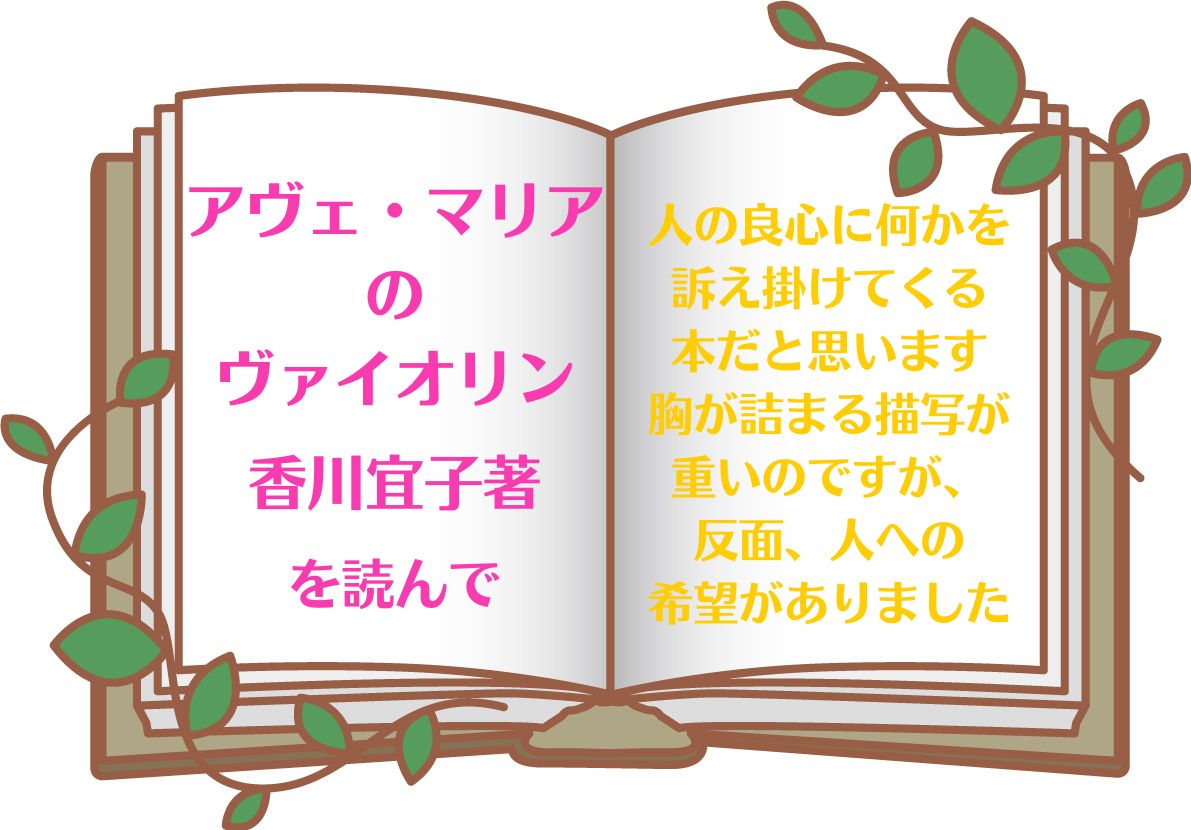ヴァイオリンと人の想いが、必要な時に必要なタイミングで巡ってきたのだと思いました。
戦争が無くならない世界で、いつでも希望の灯が僅かに残っているのが、私には期待すること以上に悲しいことのように思えます。
人はどこまでも残酷な悪魔にもなることがあり、そんな状況では大勢の人が良心に蓋をして、心を閉ざしてしまわなければ生きていけず、それが虚勢であっても胸を張って生きようとする人を妬むような世界なら、「いっそのこと全てを終わらせてしまえばいいのかも」と頭をよぎることもあります。
しかし、どれだけ残酷で愚かな行いが行われても、必ずそこには小さくても光があり、人の可能性を諦めさせない何かがあることが尊いことだと、信じたくなる時もあったりします。
「アヴェマリア のヴァイオリン」はそんな心の闇に、一条の希望の光を射してくれるような本でした。
それは、自分を含め人間のことがあまり好きでない私でさえも、感じることが出来ました。

第一次世界大戦から第二次世界大戦、そして現在に至り、一つのヴァイオリンを通して時間は遡り、希望は甦るストーリーでした。
ただ希望が響くまでには時の経過が必要だったんだろうと思います。
ナチスによるユダヤ人大量虐殺、アウシュビッツ強制収容所の描写の生々しさや、胸をえぐられるような悲しみ、登場人物の苦痛までもがこちらにまで伝わってくるような赤裸々な心模様に、読んでいて時に目を背けたくなることもありました。
その災厄の最中では、心の拠り所となる音楽ですら虫けらのように利用され、そんな中でも気丈に生きようとする一握りの人たちの心すら壊れてしまった時には、救いようのない悲しみがありました。
だけれども、一つのヴァイオリンに携わった人々の想いは諦めなかったんだと、時を経て甦ってくる人々の美しさとか強さに目頭が熱くなるのでした。
第一次世界大戦の時に、日本の徳島県の坂東という場所にドイツ兵の俘虜収容所があり、そこでは他の収容所と違い、日本人とドイツ人俘虜との間で文化交流があり、友情が芽生えた歴史があったそうです。
そこで作られたヴァイオリンが終戦と共にドイツに行き、ユダヤ人少女ハンナの手に渡り、そのヴァイオリンは再び時を経て日本の徳島県の少女の手に巡ってくる…関わった人々の想いを乗せて…
人が人に対して諦めたくなる状況でも、ヴァイオリンは諦めることなく健気にその役割を全うするのですね…深みを増した音色を響かせながら…
〈坂東俘虜収容所〉人間同士の友愛があった。

通常、戦争捕虜の話になると、劣悪な環境、人を人と思わない扱い、その他諸々、碌でもない事が大半ですが、徳島県鳴門市にあった〈坂東俘虜収容所〉では、相手を尊重して接することをモットーに、俘虜であるドイツ人と接したことで、文化交流にまでに発展し、友愛が起こったという歴史があります。
オーケストラで有名なベートーベンの「第九」が日本で初めて演奏されたそうです。
ベートーベンの「第九」は「歓喜の歌」です。
現在は「ドイツ村公園」になっています。
HanaAkari