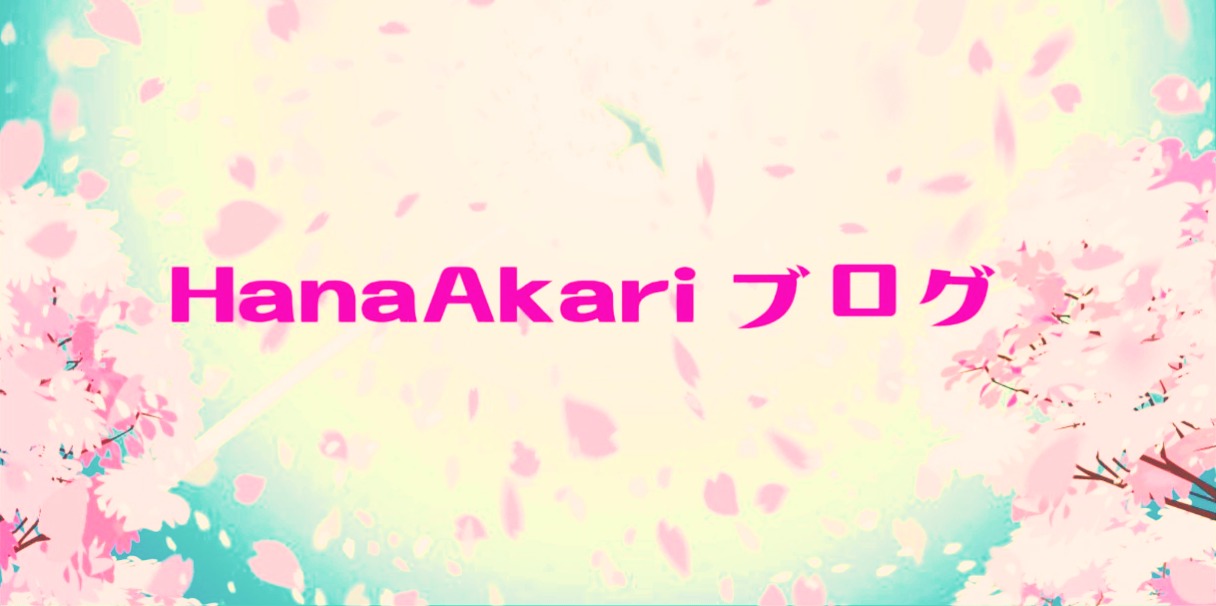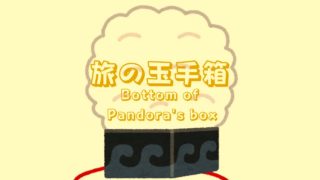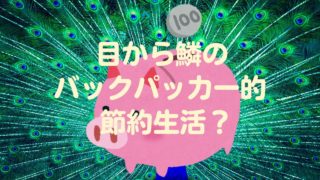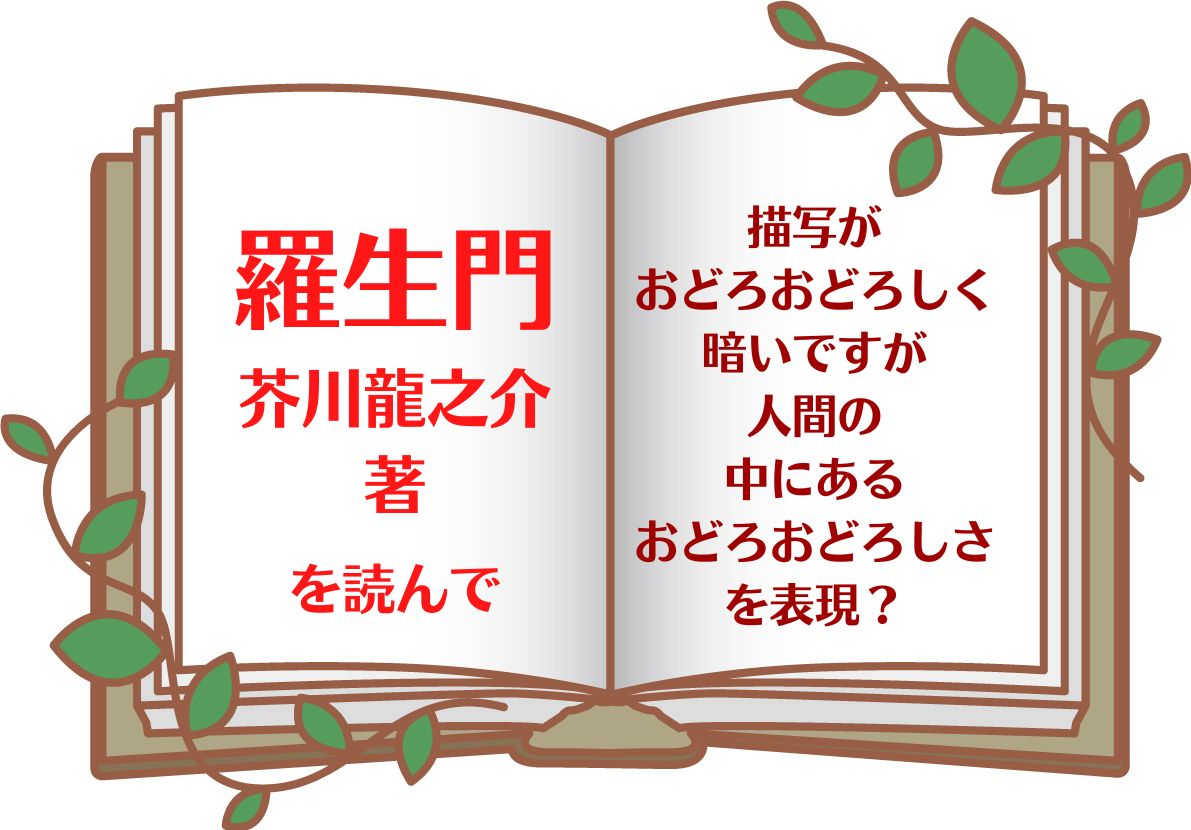「羅生門」は境界の門?人は餓鬼、修羅、羅刹にもなりえるもの
おどろおどろしい描写で暗い気持ちになりますが、その中には何か伝えたいものが含まれているのは感じ取れました。
それは読む人によって様々な解釈になって、それを上手く自分の感性の中に取り入れて、生かしていけば良いのだと思います。
京の町を未曽有の疫病や天災が襲ったのでしょう。
私はこの「羅生門」には地獄絵図のような生き地獄の世界での人の姿が、無情にも表現されていたように思いました。

辺りには死が蔓延り、その日を生きることで精一杯の世界は体験したことはありませんが、一歩間違えばすぐにでもそのような事態になる危うさの中で生きているのは確かです。
そうなってしまった時には、なりふり構わず生き延びるために、何でもありの阿鼻叫喚の世界に、自ら飛び込んで行ってしまうのではないかという不安な気持ちにもなりました。
物語の中では廃墟となった「羅生門」に住み着いた羅刹のような婆が、死体から髪の毛を抜いてカツラを作ろうとしているところに、無一文になって生き延びるためには、もう盗人になるしかないと思い悩んでいる男と出くわします。
婆の言い分は、ここで死んでいる者は死ぬ前には数々の悪行を重ねた者だから、自分がその毛をむしり取ってカツラにするのにも一理あり、因果応報なのだということでした。
それを聞いた男は婆の言い分で気が晴れたのか、盗人として目覚め、まず手始めに婆の着物を追い剥ぎします。
羅刹が誕生した瞬間でした。
羅刹とは人肉を食らう凶悪な鬼のことです。
本来「羅生門」とは羅刹のような悪鬼や悪霊、災いなどを門前払いする砦のような門なのではないのでしょうか?
そこには羅刹が巣くい、新しい羅刹も誕生するという皮肉を感じます。

以前に読んだことのある作品を、改めて楽しむという遊びを見つけました。
昔に読んだことのある作品を、時間が経過して価値観や人生観にも以前とは違いがある今、再度読み直してみることが私の一つの楽しみです。
大半のものは内容は忘れてしまっていて、タイトル名と作者だけが記憶に残っている場合がほとんどですので、以前とは違う自分が新しい作品を読むような感じになることが楽しくて、私の遊び心に火を灯してくれました。
久しぶりに読み直してみると、忘れていたはずの内容が思い出されたり、その作品を読むに至った経緯なども思い出され懐かしさも堪能できます。
まさに一石二鳥のささやかな趣味を見つけた気持ちです。
また今では、著作権が消滅した作品が「青空文庫」という電子図書で無料で読むことが出来るので、大変ありがたいことです。
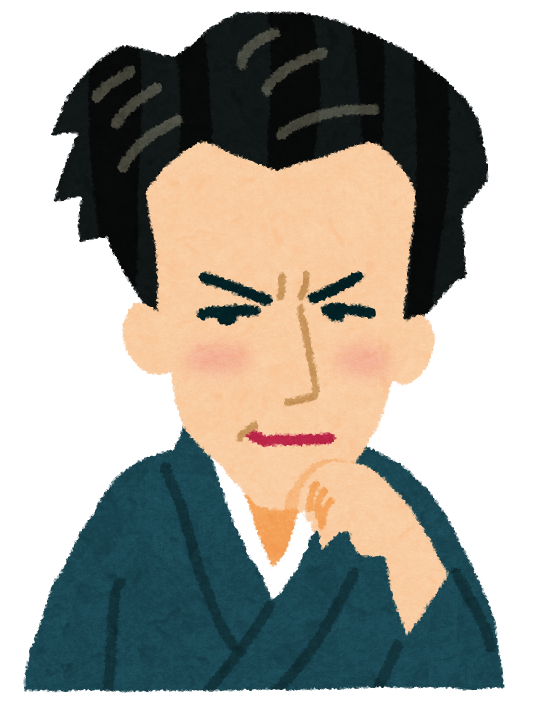
「青空文庫」とは
インターネットの電子図書館が「青空文庫」です。
「本を電子化して、誰でも読めるようにしておくと面白い」という考えから始まった取り組みで、ボランティアの方々のお陰で成り立っています。
著作権が消滅した作品が集められますので古い作品が中心になりますが、古典の名作が無料で読めることは本当にありがたいことだと思います。
日本の名立たる文豪の作品が軒並み揃っていますし、どの時代になっても色褪せない機知に富んだ作品は、後世まで残していきたいものですので、読みたい時に誰でも読めるという発想と、その取り組みは素晴らしいの一言に尽きます。
様々なテキストで読むことができるようですが、私は愛用している電子書籍〈ブックライブ〉で無料で購入できるのでそちらで読んでいます。
実を申しますと〈ブックライブ〉で0円で購入できる書籍を発見したことから、「青空文庫」の存在を知りました。
〈ブックライブ〉も有料の同じ書籍を取り扱っているにも関わらず、「青空文庫」が読めるように取り計らってくれているのにも好感が持てます。
良い発見をしました。
HanaAkari