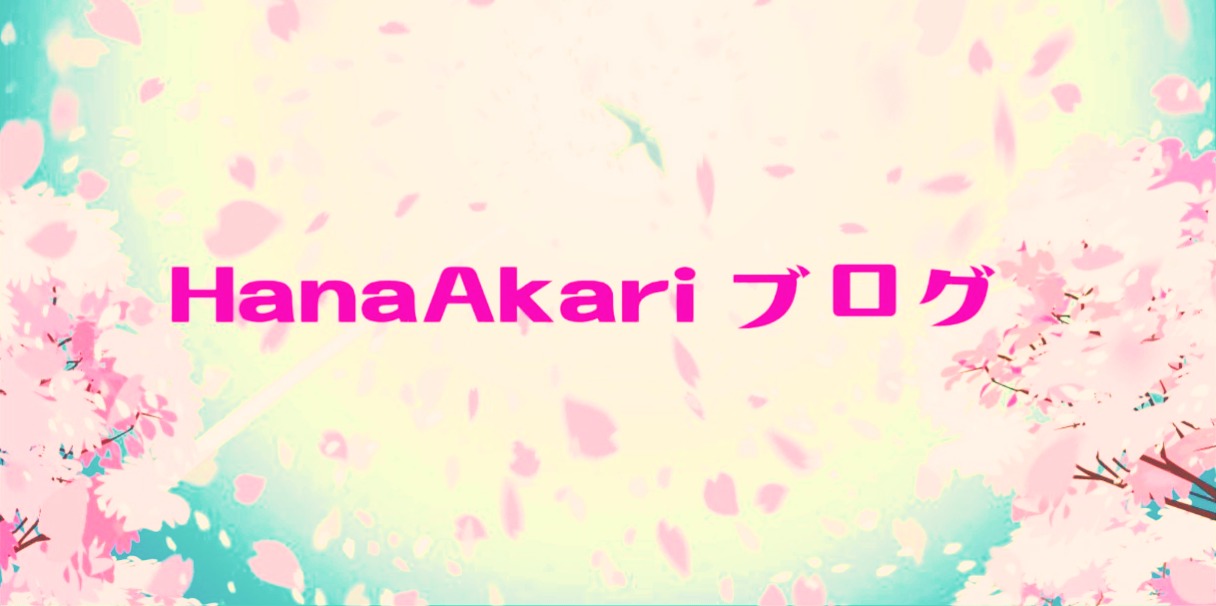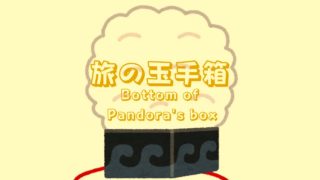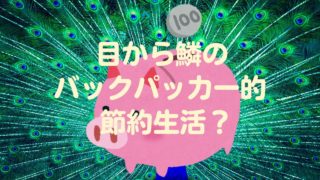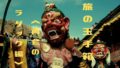- キーロン〈Keylong〉
ここから峠道を行くと〈ラダック・レー〉です。 - レー〈Leh〉
三度目の〈レー〉で再会と出会いに恵まれました。 - ラマユル〈Lamayuru〉
冬に訪れた際に偶然から家に泊めて頂くことになった縁があり、その家族に再び会いに行きました。私の旅の中でもかなり特別な出会いだったと思います。
- アティーチェ〈ラマユル〉から少し離れた場所に冬に会った時には行かなかった、夏だけ耕作可能になる畑がありました。そこに夏の家のような小屋があり、宿泊して農作業を手伝いました。〈アティーチェ〉という場所で、小さなゴンパもありました。
- レー〈Leh〉
一年前に出会ったチベタンのご夫婦との再会、韓国人旅行者との出会い、冬に訪れた際に知り合ったバクシーシのインド人との再会、仏教聖地〈サールナート〉の日本寺で会ったラダック人の家族との再会、驚く程の良縁に恵まれました。そしてこれより後は韓国人の友人らと旅を共にすることになりました。
このブログは私がバックパッカーとして、1997年9月20日出国~1999年11月16日に帰国するまでの間に訪れた場所を、四半世紀後の私が思い返してみたら、一体何が出てくるのだろうか?という好奇心から古い記憶を辿り、出てきたものを書いてみることを試みたものです。
【アティーチェと夏の家】水源の谷|旅の玉手箱 再会のラダック編-4
【アティーチェと夏の家】
〈ラマユル〉の家族と再会して数日を過ごしたある日、〈アティーチェ〉という場所に畑があるから一緒に行きましょうと誘われました。
向こうで一泊するということでした。
歩いて一時間くらいの所だそうで、〈ラマユル〉の上に抜けてお父さんと一緒にカシミール方面に道を歩いていると、ラダッキーの若い男性が数人乗ったトラックが通りかかりました。
インド軍に所属していると聞きましたが、身なりは普通で軍人ぽくは見えなかったです。
国防というよりも食い扶持を稼ぐために軍に所属しているのだろうと思いました。
あの夏にはパキスタンとインドの〈カシミール〉を巡る紛争で、小さな軍事衝突があったのは確かですが、〈カシミール〉に近い〈ラマユル〉でしたが、平和な空気しか感じませんでした。

トラックの男性たちは〈ラマユル〉の村人だったので、お父さんが少し言葉を交わすとトラックの荷台に乗せてもらえることになり、〈アティーチェ〉の入り口まで連れていってもらいました。
舗装された幹線道路から脇に入っていく未舗装の道は、軽い登り坂になっていてしばらく歩くと視界が開け、そこは山と山の間にある谷で扇状地になっていました。
そこが耕作地になっているようで、所々に石造りの小さな小屋が点在しています。
一つの小屋まで歩き、中に案内されました。
そこがその方の小屋だそうで、農作業の為の家だということでした。
小屋の入り口の前には硬い乾いた土の庭があり、石積みの低い塀で囲われていて、その周囲には畑になる耕作地が広がっている。
日本の生活とはまるで違い、昔にタイムスリップしたようでこんな生活も素敵だなと思いました。
アルプスの少女ハイジでのお爺さんが住んでいた山小屋のようで、夏の時期だけの家というのもそそられるものがありました。
しばらくすると長女と長男がヤギを連れてやってきました。
土の庭はヤギたちを繋いでおく場所の役割もあるようでした。
おそらくここのヤギは〈カシミヤヤギ〉だと思います。
〈ラダック〉は〈カシミヤ〉の語源となったインド〈カシミール〉地方の東隣にある地域ですから。

耕作地はちょうどこれから畑になっていくところでした。
畑はこれから耕していくようで、機械などはないですから手作業になります。
鍬で土を耕すのですが、標高3000メートル以上ある場所なので、私はすぐに息が上がってしまいほとんど仕事になりません。
お父さんから鍬は大きく振りかぶらずに、地面の近くを小刻みに動かして使うんだと教えてもらいました。
空気が薄い場所での体の動かし方のコツなのですが、私がそうやってみても力が入らず、土に鍬がうまく食い込まないので、どうしても大きなモーションになってしまい、息が続かないという悪循環、体得するにはしばらくこの地に住む必要があると思うのでした。
私はほとんど役に立ちませんでしたが、その日半日ほど農作業をして作業は切り上げられました。
ちょっと行くところがあるので一緒に行きましょうと誘われ、扇状地の上の方に向かって上って行ったのですが、途中に水が少しづつ湧き出ている箇所があり、それがここらの畑を潤すための水源で、川が生まれる場所だったのです。
水源を見られたことが嬉しかったです。
雪解け水が湧き出て、それが細い小川となって流れるので、あそこは夏の時期には耕作が可能になるのでしょう。
そして〈インダス川〉に合流するのでしょう。
私は生まれたての水はどんな味がするのだろうと思い、飲んでみたくなりました。
そして水が湧き出ているすぐ近くでペットボトルに汲んでみましたが、地面から染み出ているような感じなので水深はほとんど無く、水だけを綺麗にすくえずにどうしても不純物が混じってしまいました。
後日談ですが、その水を布で簡単にこして飲んでみたら、お腹は下しませんでしたが、腹に張ったような違和感が起こり、おならが止まらくなる現象がしばらく続くことになりました。
多分、生水を飲んだことによる何かしらの微生物による悪戯だったのだと思いますが、自然と収まったので幸いでした(笑)

〈アティーチェ・ゴンパ〉小さな僧院と老僧侶
扇状地の最上部まで上った所に、小さな〈ゴンパ〉がありました。
〈アティーチェ・ゴンパ〉と教えられましたが、〈ゴンパ〉とは僧院という意味で、これまでに〈ラダック〉の各地で見た〈ゴンパ〉のように、大規模で僧侶が大勢いるものとはまるで趣きが違いました。
こじんまりとしたひなびたお堂がいくつかあって、一つの小屋に一人の老僧侶がいるだけでした。
時代の流れで消え去っていく場所のような印象を受けましたが、その時にしかない黄昏の情緒は嫌いではありません。
お父さんは老僧侶に挨拶を交わし、〈ゴンパ〉の中を見せてくれました。
古い色褪せた仏像は、それはそれで良いものでした。
バター茶を御馳走になりながら、面白い話を聞きました。
以前、一人の日本人男性がこの〈アティーチェ・ゴンパ〉で、何カ月も瞑想していたことがあるというのです。
小さなお堂の一つを指さして、あそこでずっと瞑想していたと教えられました。
「御飯はどうしていたのか?」凡人の私が真っ先に尋ねた質問の答えは、村人が差し入れしていたということで、その時はすんなり受け入れましたが、後ほどよせばいいのに頭を使って考えてみると、とてつもない話だと思わざる得ないのでした。

〈アティーチェ〉の夜
電気がない生活では、まだ明るいうちに用事を済ますのが習慣になります。
夕刻、〈アティーチェの夏の家〉に戻ると、夕飯の支度でした。
長女が主になって簡単な夕飯が容易され、暗くなると真っ暗ですから後は眠るだけです。
そして次の日の朝、日が昇る頃には動き出す、自然のサイクルに沿った生活でした。
HanaAkari