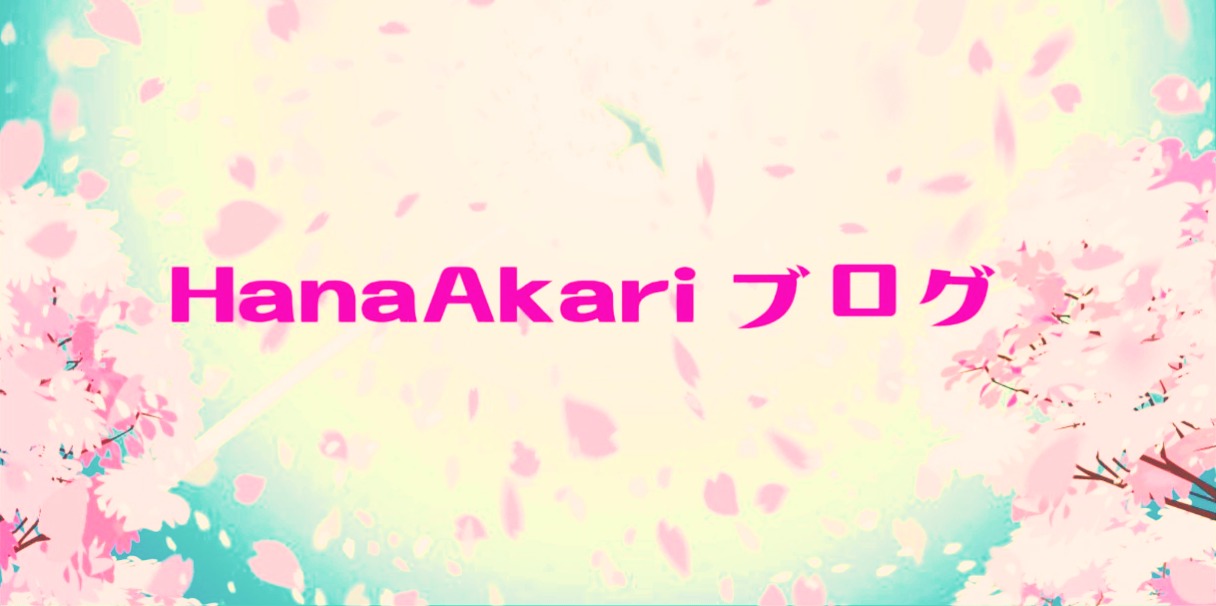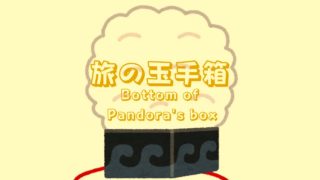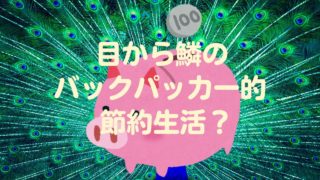真田家の家紋が「六文銭」のことからも真田の覚悟が感じられます。
なかなか出来ることでは無いですが、正しく「覚悟」を「愛」の方向に使っていけば、未来はよりよい方向に向かっていくのではないのかな。
このブログは言葉から連想したことを自由に書いています。時に勇気や喜びをもらえたり、慰められたり、癒されたり、言葉には力があるように思います。そんな素敵さや楽しさを少しでも表現できたら幸いです。
【真田丸】大阪冬の陣ゆかりの場所は今では学びの場|言葉の小槌57
【真田丸】
戦国の世に「大阪冬の陣」が始まる前に「真田幸村」が築いた、「偃月城」通称「真田丸」があった場所は小高い丘になっていますので、その「砦」は高台の有利さと見晴らしの良さで、とても合理的だったのだろうと容易に想像ができます。
さらに大阪城の出入り口に向かって侵入してきた徳川側の兵に、大阪城側と真田丸側から鉄砲隊が集中砲火を浴びせる構造になっていたようで、最前線に陣取る豪胆さ「勇」と知恵の「知」を併せ持つ幸村ならではの発想が形となった恐るべき「砦」だったことでしょう。

真田家の家紋「六文銭」は「三途の川」の渡し賃
真田家の家紋が「六文銭」のことからも真田の覚悟が感じられます。
「三途の川」の渡し賃が「六文」とのことで、死と隣り合わせの戦場のこと、常に「死」を意識して臨んでいたのだと想像できます。
また「死」を覚悟しているからこそ、その時を思いっきり生きていたのでしょう。
「大阪夏の陣」では圧倒的不利な状況でも不屈の精神で最後まで戦い抜いた、幸村の力の根源は「覚悟」だったのかもしれないと思うのです。
ただやみくもに突っ込むのではなく、知略を尽くして起死回生の必殺の一撃を狙い、突撃する渾身の姿に心を打たれてしまいます。
伝説になるのも納得ですし、「真田十勇士」といった想像も生まれるのもレジェンドですから当然のように思いました。
戦争を肯定したい訳では決してありませんが、何事も「覚悟」を持って臨むべきなのではないかと思います。
なかなか出来ることでは無いですが、正しく「覚悟」を「愛」の方向に使っていけば、未来はよりよい方向に向かっていくのではないのかな。
「覚悟」と「愛」は似ていないようですが、おそらくどちらも必要で二人三脚で進むことで、良い方向に向かうような気がします。
かつての戦場は現在では「学びの場」
現在は「真田丸」があったとされる場所は「大阪明星学園」のグラウンドになっていて、道路沿いに「真田丸顕彰碑」がありました。

当時は火縄銃が火を吹き、轟音が響き渡っていたことでしょうが、私がその場所を訪れた時はソフトテニスのクラブ活動が行われていて、「ポン」「ポン」とボールを打つ音が聞こえてきました。
なんだか可愛くて、「平和」の音だなぁ~と嬉しくなりました。
学園沿いを歩いていくと、体育館から元気なクラブ活動の声が聞こえてきて、かつての戦場も今はこうなのだと、ほっこりしました。
HanaAkari